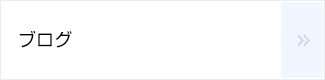三越の包装紙に包まれたアルミのお弁当箱を開けると、ふっくらとした白いご飯の横に分厚い卵焼き、塩鮭、赤い煮豆、そしてシャキッとした白菜のおしんこが並んでいる。これを作ってくれたのは、「きみちゃん」と呼ばれていたお手伝いさんだった。
時代は昭和四十年代。私は高校一年生だった。その年、父の三度目の転勤が急に決まり、学期半ばで一人仙台に残ることになった。私を二ヶ月間預かってくれたのは、父の知人で小さな会社を営む佐藤辰蔵さん一家だった。洋風の古びた家に、佐藤さん夫婦と、私と同じ高校に通う一年先輩の瑠美子さん、小学生の憲太君、そして月曜から金曜まで住み込みの「きみちゃん」が暮らしていた。
きみちゃんは無口で、日焼けした肌に白髪混じりの長い髪を後ろで束ね、黙々と働いていた。料理好きで、気づくといつも台所に立っていた。時々思い出し笑いでもしているのか、一人でにやにや笑っていることがあったが、笑うとどっきりするほど老けて見えた。剥き出しになった上の歯茎に一本も歯がなかったからだ。
さて、そんなきみちゃんの二日目のお弁当は、卵焼き、塩鮭、煮豆、白菜のおしんこ…まさかの前日と全く同じメニューだった。私は驚きすぎて、すぐには食べる気になれなかった。
さすがに三日目も同じなんてことはないだろうと思ったが、学校に着くや否やお弁当箱を開けてみた。手渡してくれたとき、心なしかきみちゃんがにやりと笑ったように思えたのだ。案の定、レギュラーの四品が定位置に並んでいた。
「三日も同じなんてあり得ない!」と心の中で叫んで、私はお弁当を机の奥へと押し込んだ。
なぜ料理上手なきみちゃんがこんなことをするのだろう。売店で買ったパンをかじりながら私は思いを巡らせた。そんな中、ふと気づいたことがあった。佐藤家に来た最初の日、こまっしゃくれた憲太君がいきなり「きみちゃんは何歳だと思う?」と聞いてきたのだ。化粧もせず、萎びた乾燥芋のようなきみちゃんの年齢なんて、正直見当もつかなかった。
「もう八十歳なんだよ」
憲太君はニヤニヤしながら言った。お茶を注いでいたきみちゃんも、どこか面白そうに聞いていた。驚いた私はつい、
「嘘でしょ! もっと若いよね」
「六十歳ぐらい?」
と、口走ってしまったが、これが運の尽きだった。
後で聞いた話では、きみちゃんの実際の年齢は四十代後半だったらしい。その時、きみちゃんの顔が引きつり、周囲の空気が一瞬で凍りづいたのをはっきり思い出した。彼女の目がギラリと私を睨んだのも。
四日目のお弁当はもはや開けてみるまでもなかった。これは明らかに仕返しだとわかったからだ。
帰り道、広瀬川にお弁当の中身をそっと流しながら、私は「いかなる場合でも、女性に年齢のことを言うのは絶対に避けるべきだ」という人生の教訓を得た。
家に戻り、小さな声できみちゃんに「お弁当はもういりません」と告げると、彼女は歯茎をむき出しにして、勝ち誇ったようにニヤリと笑った。
それから一年後、驚くべきニュースが舞い込んできた。きみちゃんは、佐藤家以外にも週末に通いで行っていたT大学の教授と結婚し、なんと教授夫人になったというのだ。純情な高校生だった私には怪奇現象としか思えなかった。

(写真は本文とは関係ありません)
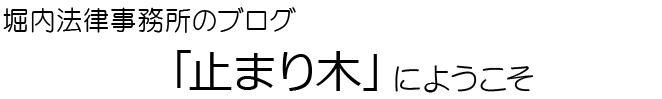
 当ブログでは、事務所のスタッフ(+α)が、身近な四季の風景や、思い出の風景、
おすすめの本の紹介などを綴りながら、
ここでちょっと羽休めをしております。
当ブログでは、事務所のスタッフ(+α)が、身近な四季の風景や、思い出の風景、
おすすめの本の紹介などを綴りながら、
ここでちょっと羽休めをしております。